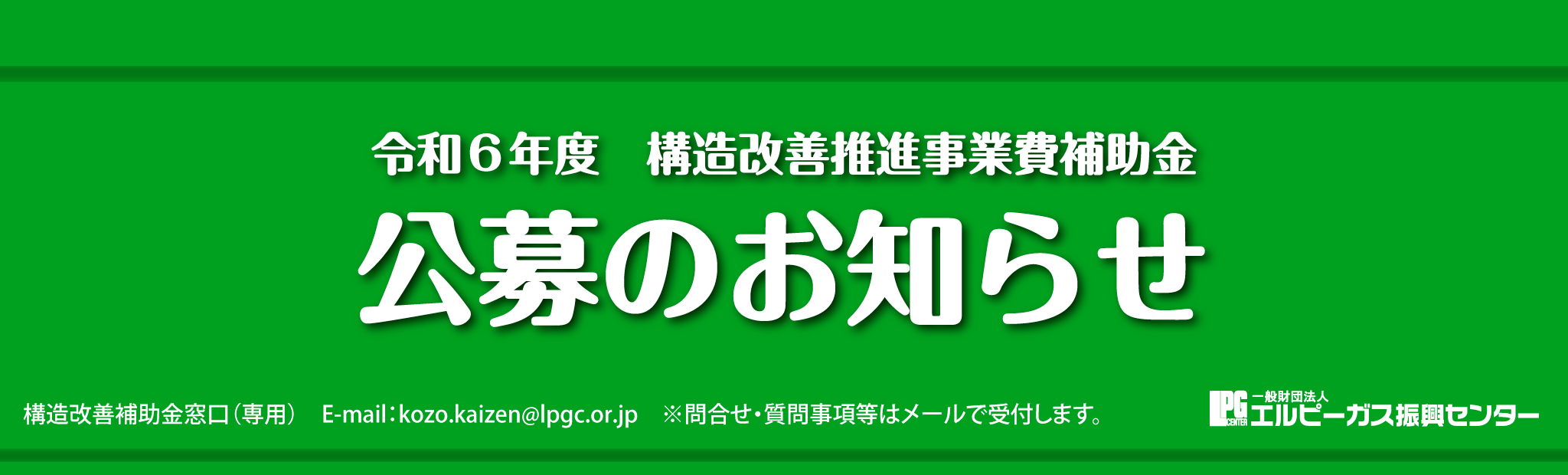交付申請 編
中小企業に該当するかを判断していただけるしょうか。
当センターでは判断できないので、いたしません。
中小企業に該当するかどうかは、主たる業がどのような業種であるかによりますので、中小企業基本法第2条第1項の規定を中小企業庁のホームページでご自身でご確認ください。
また、本補助金では、中小企業基本法上では中小企業であっても、申請者(共同申請者が補助対象設備機器の運用・維持・管理者である場合は共同申請者)が
1.資本金又は出資金が5億円以上の法人に※直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者、
2.交付申請時において、確定している直近過去3年間の各年又は各事業年度の課税所得平均額が15億円を超える中小・小規模事業者の場合、中小企業ではないとの扱いをいたしますので、ご注意ください。
この場合、課税所得額は納税証明書その2に記載の更生・決定額の額となります。なお、補助金交付後に中小企業に該当しないことが明らかになった場合、交付取り消しとなり、補助金を全額返還していただきますので、十分確認の上、申請してください。
※直接又は間接に100%の株式を保有されるとは
①株主が単独の法人でその法人が資本金又は出資金が5億円以上の法人の場合
②株主が単独の法人であるが①に該当しない場合、その法人の株主が資本金又は出資金が5億円以上の法人の場合
③100%株式保有の親会社が続く場合は確認ができるまで遡ります。
交付申請書類の事前チェックは、お願いできますか。
交付申請書類の事前チェックは、いたしません。
申請に必要な様式等の質問や申請予定事業が補助事業に該当するか等については、申請者用のホームページをよく確認いただき、分からない場合は相談に応じます。
事業効果額とは、何ですか。
補助事業の事業効率を表すものです。
補助対象経費総額を機器設置予定件数で割って算出し、申請された補助事業がどれくらい効果的に実施できるのかを数値化したものです。
事業完了後の事業効果額が、申請時と大きく変わらないことを確認しますので、申請時から、適切な契約手続きにより、低廉かつ合理的な効果額での取り組みとなっている必要があります。
申請する際、補助金の対象となる総事業費(補助金額)に上限や下限はありますか。
あります。
申請できる1件当たりの総事業費は、上限6,000万円(補助金額3,000万円)、下限100万円(補助金額50万円)です。
過去交付実績があっても補助申請は可能ですか。
可能です。
令和5年度補正「石油ガス配送合理化・設備整備補助金」を含め、過去交付実績の有無による不可否はありません。
しかしながら、現状の導入率が低い者の申請が優位になるので、詳しくは申請者用ホームページを参照してください。
公募締切後の交付決定のスケジュールについて、予定を教えてください。時間がかかる場合、交付決定前の作業として、見積依頼先に機器の発注を始めていて良いでしょうか。
交付決定前に発注を始めてはいけません。
公募締め切り後、当センターで審査を行い、審査委員会における審査を経て交付決定が行われるまで1か月以上かかります。
その場合でも、設備機器等の発注・施工等事業の具体的な活動に関しては、交付決定後としてください。交付決定前に発注・施工した場合、その事業費用は補助対象外となります。
導入率を算出するための総顧客数とはどのようなものですか。
総顧客数は、原則として、液石法に基づく直近の「液化石油ガス販売事業報告」記載の「空室を含む全営業所の顧客数の合計」を一般消費者等の数とします。
補助事業の完了とは、どの時点をいいますか。
補助事業の完了とは、全ての通信機器の取得・設置工事が終了し、通信機器のデータが正常に取得されたことを確認した後、補助事業に要する経費総額の支払いが終了した時点を補助事業の完了といいます。
本年度は、遅くとも令和7年2月14日までに、補助事業を完了しなければいけません。
補助金の支払いは、いつ頃になりますか。
補助事業完了後の実績報告書提出から少なくとも1か月程度はかかる見込みです。
当センターは、実績報告書の内容を審査の上、確定通知書を送付します。補助事業者は、確定通知書を受領後、7日以内に精算払い請求書を提出してください。その後、当センターから振り込みをするという流れになります。
補助事業によって設置した機器等で、使用料等を徴収することはできますか。
使用料等を徴収することはできません。
使用料等を徴取すると、その事業は営利目的と判断され、そもそも補助対象とするべきではなかったということになります。
本補助事業の目的は、補助事業によって構築されたノウハウが、系列を超えて業界全体への波及する効果を見込むことにあります。
万が一徴収されていた場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還となる場合もありますので、ご注意ください。
機器設置の証明として、写真の撮り方はメーターと発信機等(親機、中継機)が別にある場合、それぞれ必要ですか。
それぞれ必要です。全ての機器写真を撮影、保存することが必要です。
なお、事業完了後の実績報告時に「機器の設置写真」の提出は求めませんが、これをもとに「導入先並びに開通記録に関する報告書」を作成していただき、提出を求めます。
事業区分1の機器とLPWAとの違いはなんですか。古い機種を廃棄して設置する場合は申請できますか。
区分1は24時間に1回以上検針が可能なものであり、LPWA機器が含まれます。
従来の月1回などの検針機器は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
ただし、申請書様式1の5.通信機器等設置に関する計画及び基準の「導入済の集中監視件数」には、従来型の月1回検針機器も含めてください。
古い機種を廃棄して交換設置する場合も申請可能です。但し、交換設置のみでの申請はできません。
必ず、交換以外に新規の需要家へも設置し、事業完了後の導入率が事業開始前より上回っている必要があります。
導入率の考え方を教えてください。
原則、集中監視(従来型の有線やFOMAを含むすべて)に関する導入率を指します。
集中監視総数を空家・空室を含む顧客数で除した割合を導入率とします。
業務細則第6条第1項にある補助対象となる申請者で、「リース事業者」、「協同組合」とは、具体的にはどのような者ですか。
「リース事業者」とは、
定款にリース業の記載がある事業者で、リース事業者が申請者となりLPガス販売事業者と共同で補助事業を実施することが可能な者です。
「協同組合」とは、
LPガス販売事業者が組合員である協同組合で、その定款上、組合としての顧客ではなく、組合員であるLPガス販売事業者の顧客を対象とした構造改善事業を共同で実施することがふさわしい内容であり、かつ当該組合員が単独で同時期に構造改善事業を実施しないと判断される者です。
共同申請者がある場合の提出書類に追加はありますか。
基本的にリースを活用する場合には、共同申請者が発生します。
共同申請者がある場合は、EXCELシートのP2、3の共同申請者欄について記入してください。該当する事業者について全ての提出書類を用意していただきます。本ホームページの「申請に必要な書式等」、「申請方法の説明」を参照してください。
変更 編(様式第6、様式第7)
計画変更の手続きについて教えてください。
【計画変更等承認申請(様式第6)に該当する場合】
●機器の導入件数の減少(増加は認められません)
原則として、申請時の導入予定件数の10%超の減少となる場合
~その計画変更に係る事業実施前に「計画変更等承認申請書(様式第6)」及び見積書等必要書類を当センターに提出し、その承認を得る必要があります。
【計画変更届出書(様式第7)に該当する場合】~変更内容と提出書類
●事業完了日:「計画変更等届出書(様式第7)」
●代表者変更:「計画変更等届出書(様式第7)」、登記事項証明書、株主総会(取締役会議)議事録コピー
※代表者以外の役員変更は不要。実務担当者が変更の場合はメールにて連絡ください。
●住所変更:「計画変更等届出書(様式第7)」、登記事項証明書
●機器導入件数の減少(増加は認められません):「計画変更等届出書(様式第7)」、見積依頼書、見積書、注文書、注文請書等申請時の導入件数の10%以下の減少となる場合
●通信機器の機種変更、メーカーの変更(導入件数に変更がない場合):「計画変更等届出書(様式第7)」、見積依頼書、見積書、注文書、注文請書等
※変更事案が発生してから相当な期間が経過している場合や変更申請の提出期限を過ぎている場合などは、代表者名で顛末書や始末書を提出して頂きますので十分注意してください。
※新規設置件数と交換設置件数について、申請時の件数と実績報告時の件数が異なっても、合計件数に相違がない場合、減額等の対象になりません。ただし、新規設置件数が0件の場合は交付申請対象外となりますので注意してください。
実績報告 編
分割納入・分割請求・分割支払について教えてください。
●分割納入:可能です。(都度納品書・受領書を完備)
●分割請求:可能です。(月毎の請求単位で統一)
●分割支払:原則一括支払いとします。ただし以下の条件に限り可能とします。
【現金振込支払いの場合】
原則は「7日間連続の設置先データ確認後一括支払」とします。
~特例として、与信管理・回収サイト等々の関係上「月毎の請求書単位の分割支払」を可能とします。
ただし、次の事項は厳守願います。
1.該当月の請求書は「構造改善専用」とすること。
※構造改善専用とは、本補助金に該当するものだけを請求する請求書のこと。
2.支払いは請求書通りに単独で支払い、「振込手数料」は毎回支払者の負担とすること。
※単独で支払うとは、上記1.の請求書の金額だけを支払うことを言い、同じ支払先でも他の請求(商品代)等をまとめて支払わないこと。
3.最終支払日が「事業完了日」となるため、全ての設置先データが7日間連続取得を確認の上、支払をしてください。
※事業完了(完全データ取得)前に支払を済ませた場合は、「返金」後「再振込」をしていただきますので、充分注意してください。
【リース契約の場合】
申請者であるリース会社の契約条件に則ってください。不明な点はリース会社に問合せ願います。
支払依頼書
× 振込依頼書の出力日付が、振込日以前のもので実績報告する。
ネットバンキングにて支払依頼をする場合は、出力するタイミングに注意し、依頼日には出力せずに後日振込確定後に出力をお願いします。
例)令和6年12月25日に振込をする場合
①事前に振込依頼をする
②振込依頼書を出力する
× 令和6年12月24日に出力
〇 令和6年12月26日に出力
※実績報告時に提出していただく振込依頼書が振込日以前のものは再度出力を依頼します。
※振込日以降に帳票が出力できない場合は銀行からの「振込確認書」を用意していただきます。
導入先並びに開通記録一覧・設置工事完了報告書(施工記録写真)関係
× 書式が異なる
昨年度の様式や独自の様式を使用しないでください。
導入先並びに開通記録一覧や設置工事完了報告書は提出不要ですが、これらの書類を元に「導入先並びに開通記録に関する報告書」を作成していただきますので、書式が異なると正しく作成できない場合が懸念されます。
尚、提出は求めないものの作成のうえ手元で保管管理してください。交付後、国における検査等で確認する場合もあり得ます。
以下に作成上の主な注意事項を記載します。
・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働確認欄が「×」の場合、理由を必ず記載する。
・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働データは、7日間連続となっていること。
⇒データ確認欄がすべて「7」となっていること。
・設置工事完了報告書の写真は全設置先をすべて作成すること。
⇒設置先すべてに対し「施工前・施工後」を撮影してください。
・設置工事完了報告書の「写真の看板の文字」が鮮明に読み取れるようにすること。
(小さい・ピンボケ等のないこと)
⇒工事後の写真を再度取り直しとなります。工事担当者に充分周知願います。
よくある間違い 編
総顧客数
× 消費実績のある顧客のみカウントしている。
× 実績報告書が直近のものではない。
原則、液石法第132条に基づく直近の事業報告書により確認します。
空家・空室が明確化されている場合はその数を必ず含めてください。
支払依頼書
× 振込依頼書の出力日付が、振込日以前のもので実績報告する。
ネットバンキングにて支払依頼をする場合は、出力するタイミングに注意し、依頼日には出力せずに後日振込確定後に出力をお願いします。
例)令和6年12月25日に振込をする場合
①事前に振込依頼をする
②振込依頼書を出力する
× 令和6年12月24日に出力
〇 令和6年12月26日に出力
※実績報告時に提出していただく振込依頼書が振込日以前のものは再度出力を依頼します。
※振込日以降に帳票が出力できない場合は銀行からの「振込確認書」を用意していただきます。
導入先並びに開通記録一覧・設置工事完了報告書(施工記録写真)関係
× 書式が異なる
昨年度の様式や独自の様式を使用しないでください。
導入先並びに開通記録一覧や設置工事完了報告書は提出不要ですが、これらの書類を元に「導入先並びに開通記録に関する報告書」を作成していただきますので、書式が異なると正しく作成できない場合が懸念されます。
尚、提出は求めないものの作成のうえ手元で保管管理してください。交付後、国における検査等で確認する場合もあり得ます。
以下に作成上の主な注意事項を記載します。
・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働確認欄が「×」の場合、理由を必ず記載する。
・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働データは、7日間連続となっていること。
⇒データ確認欄がすべて「7」となっていること。
・設置工事完了報告書の写真は全設置先をすべて作成すること。
⇒設置先すべてに対し「施工前・施工後」を撮影してください。
・設置工事完了報告書の「写真の看板の文字」が鮮明に読み取れるようにすること。
(小さい・ピンボケ等のないこと)
⇒工事後の写真を再度取り直しとなります。工事担当者に充分周知願います。